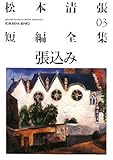今年最初の更新でも、またまた松本清張作品を取り上げる。清張以外の小説も読んでるし、小説以外の本も読んでいるのだが、清張作品の場合、作品の背景を調べてみるといろいろ興味深いことを知ることができる機会が多いので、どうしても取り上げる頻度が増える。
5年前の2013年11月に『Dの複合』を読み、それまで食わず嫌いならぬ読まず嫌いだった清張ワールドに一転してはまって以来、清張作品を読むのももう5年目に入り、3年目に入った2015年末以降は、清張作品をどれだけ読めるかにチャレンジしている。すべて図書館で借りた文庫本で読み、読んだ本の冊数は上下本を2冊と数えると既に96冊に達したが、それでも推理小説を含む現代小説の長編でようやく半分を少し超えたところで、短編小説は未読の方が多いし、時代小説に至っては読んだ方が未読よりもずっと少ない。図書館に置いてある文庫本は、人気のある推理小説の長編が多いせいもある。
清張が芥川賞をとった短編「或る「小倉日記」伝」は以前からの懸案だったが、この作品を含む新潮文庫の傑作短編集第1巻が図書館になかなか置いてないので読むのが遅れた。そうこうしているうちに、昨年光文社文庫からリニューアル出版された「鴎外の婢(ひ)」を先に読む羽目になった。
「鴎外の婢」は1969年の作品で、光文社文庫の「松本清張プレミアム・ミステリー」では「書道教授」(1970)が併録されている。この2作は、『週刊朝日』に連載された連作「黒の図説」の第3話と第4話に当たる中篇小説だ。単行本初出は光文社のカッパ・ノベルスで1970年刊だが、1974年に新潮文庫入りしており(絶版)、以下の作品紹介は新潮社のサイトによる(2012年に電子書籍化されている)。
www.shinchosha.co.jp
また、ネット検索で知った大津忠彦氏の論文「松本清張著『鴎外の婢』にみられる考古学的虚実構成」によると、カッパ・ノベルス版『鴎外の婢』(第29版、1973年10月5日発行)のカバー折り込み部に、
「鴎外の婢」は出世作『或る「小倉日記」伝』を書き、最近「魏志倭人伝」の謎を学問的に究明した『古代史疑』を書いたこの著者でなければ、到底着眼できぬ独創的な状況設定である。
と書かれていたそうだ。
「鴎外の婢」に盛り込まれた、小倉時代の森鷗外、それに清張得意の考古学に関する蘊蓄がなかなか面白かったので、モデルと実在の人物の対比、つまりどこまでが史実でどこからが清張の創作した虚構なのかをネットで調べながら読んだ。
と同時に、懸案だった「或る「小倉日記」伝」を含む短篇集もそろそろ読まなきゃなあと思ったのだった。図書館に新潮文庫版の傑作短編集が置いてなかったことと、区内10箇所の図書館にバラバラではあるけれども全巻を読むことができる(たとえば第2巻は某館にしか置いていないけれども、その図書館には第1巻が置かれていないなど)光文社文庫版の「松本清張短編全集」全11巻を読むことにした。これは1962年にカッパ・ノベルスから刊行されていたものを2009年の清張生誕100周年に合わせてリニューアル出版されたもので、「全集」とは銘打たれているが1962年までの作品しか収録されておらず、かつ前回のエントリで紹介した『黒い画集』からは収録されていない。
これまでに読んだのは第1巻と第3巻。
「或る『小倉日記』伝」は第1巻に収録されている。この作品は芥川賞受賞作にして坂口安吾に絶賛されただけのことはあって、これまで読んだ清張作品中でも屈指の名作だと思うが、この作品については既に語られ尽くしていると思われるので、ここでは取り上げない。
今回は、第3巻に収められたいくつかの作品について書く。短篇集全体としてとらえた場合、この第3巻の方が第1巻よりも面白いと思った。
第3巻で最初に強い印象を受けたのは、清張の最初の推理小説として知られる「張込み」ではなく、第3巻の3番目に置かれ、かつこの短篇集の中ではもっとも早い1953年に書かれた「菊枕」だ。
これは、俳人・杉田久女(1890-1946)をモデルにした小説だ。杉田久女は松本清張と同郷の小倉の人だ。久女の略歴については、たとえば下記読売新聞記事を参照されたい。
www.yomiuri.co.jp
カッパ・ノベルス版及びそれを復刻した光文社文庫版の「あとがき」で、清張は下記のように久女を評している。
久女の俳句については今日すでに声価が定まっているので、ここに言うことはない。この天才的な俳人は、実は小倉中学の絵画教師の妻だった。彼女は、虚子や、その周辺の巨大グループに接してからは、ひどくその境遇に劣等感をもち、家庭は必ずしもあたたかではなかった。その性格の強さは虚子を偶像化し、その周辺に向っては限りない敵意を燃やした。小説の題は「ちなみぬふ陶淵明の菊枕」からとったが、久女が縫っていた菊枕は、中国に伝わる長寿の徴にと虚子に献じたのであった。この取材のため私は奈良まで行き、久女のかつての弟子だった橋本多佳子氏や、『天狼』の平畑静塔氏などに会った。もとより、地元の俳人からも話しを聞いた。その一人の女流俳人が「どんな題をつけるの?」としきりにきいたが、てれくさくて最後まで明かさなかったのを覚えている。(光文社文庫版325頁)
同じ光文社版短編全集第3巻に続けて収録された、後述の「断碑」及び「石の骨」を読むと、久女と同じく恵まれない環境にいた清張が久女に深い共感を寄せていたことがわかるが、しかしながら清張による「ぬい女」(杉田久女をモデルにした主人公)の描写はあまりにエキセントリックで、それが久女の遺族を怒らせ、清張は久女の遺族から名誉毀損で告訴されてしまったのだ。たとえば久女の長女・石昌子(1911-2007)は、1992年に福岡シティ銀行常務取締役だった本田正寛氏との対談で、次のように述べている。
石
吉屋信子さんの評伝「底のぬけた柄杓」にとりあげられてから、俳壇や、地元や、ラジオ・テレビや、小説・演劇まで、久女のことが滅茶苦茶で悲しかったですね。松本清張さんの「菊枕」も、久女にはあまりにもきびしい作品でした。
本田
それらが次々と孫引きされて誤った久女像が世間を歩きだすのですね。
でも宇内先生に絵を習われた増田連さんが「杉田久女ノート」でその誤りを実に明確に指摘されている。石さんは内側から、最近は田辺聖子さんや澤地久枝さん、上野さち子さんといった方たちが、外側から久女像を描いておられる。次第に、ありのままの久女がよみがえってくるのですね。
石
そう。ありがたいですよ。死後、久女は小倉に受け容れられなかった。父も母も、それぞれ小倉の文化面につくしています。だのに逝くなってから、悪く扱われるばかりだったでしょう。
本田
そういう事もあったのでしょうね。
でも、いまは市が音頭をとって、久女を北九州の立派な俳人と、誇りにしています。時の流れが、久女をおおっていた濁りを洗いながしているのでしょうね。
清張が書いた「歪められた」久女像には、吉屋信子という先人がいた。私は類似の事例に昨年接したばかりだったことを思い出した。それは伊藤律である。律は特高のでっち上げによって「仲間の共産党員を売ったスパイ」に仕立て上げられた。その特高が捏造した虚像に飛びついたのが、ゾルゲ事件で処刑された尾崎秀実(1901-1944)の異母弟・尾崎秀樹(1928-1999)だったが、その尾崎秀樹による伊藤律像を拡散したのが清張だった。伊藤律像を歪めたのは特高だったが、杉田久女像を歪めたのはどうやら師の高浜虚子であったらしく、久女ファンの間では虚子の評判は散々だ。久女ファンが虚子を糾弾する文章もいくつか読んだが、長くなるので引用等は割愛する。
ただ、今回のネット検索で一番興味深かったのは、久女の夫であった杉田宇内(うない)の教え子が今も健在でブログを書いているのを知ったことだった。ブログの記述を信頼すればブログ主は今年で満89歳くらいと思われるが、今でも元気にブログを更新している。残念ながら、右寄り、かつ少なくとも一頃は小沢一郎を熱烈に応援していたとおぼしきブログ主の政治的立場や書かれている時事評論にはほとんど同意できないが、杉田宇内にまつわる記事は興味深い。その中から、下記のブログ記事を引用しておく。
『春雨や畳のうえのかくれんぼ』 久女
“我ときて遊べや親のないすずめ” “そこのけ、そこのけお馬が通る”の一休和尚を彷彿させ、自然に童謡を口ずさみたくなる秀句である。
悪戦苦闘しながら三週間かけてやっと、湯本明子の力作『俳人杉田久女の世界』を読み終えた。
文才のない私が書評なんて大それたことは出来ないが、寸評を書いてみる。
久女を語るとき、夫の宇内は避けて通れないが、田辺聖子の名作『花衣ぬぐやまつわる・・・』でさえも、宇内が的確に描かれていない。まして、松本清張『菊枕』、特に吉屋伸子『私の見なかった人』に至っては、風聞だけを基に、悪意に充ちている。そもそも天下の名門・お茶の水高女卒業の才媛の久女が、上野の美術学校(現東京芸大)研究科中退の宇内に嫁いだのは、未来の画家夫人を夢みたからだというのが、人口に膾炙し、三人の小説にも書かれている。ところが、夫は画筆を執るどころか、小倉中学の教師に埋没し、休みの日には魚釣りに明け暮れ、久女はストレス発散の意味から、兄の手ほどきで作句に走ったといわれている。
三人の小説のネタの基は、増田連の『杉田久女ノート』だが、彼は、私の一級後輩で、実に丹念によく調べているし、よく久女の俳句を研究し頭が下がるが、宇内については、調べていないというより知らなかったと思われる。
私は、宇内先生(あだ名は、バネさん)の教え子として、名誉回復と誤解を解くため一筆書いてみる。その点、湯本明子の作品は、宇内の正確な評価が書かれて嬉しかった。歴史にifはありえないが、宇内がもし画筆を執っていたなら、天才閨秀俳人が生まれたかどうか。反面教師の感がする。
教師の第一の勤めは、生徒の氏名を覚えることだが、彼は、一期生から私たちの三十五期生まで、全員フルネームで覚えておられた。図画(美術)の教師だから、たった一年だけしか教えていないのに・・・。
同窓会総会には、先生は愛知の山奥から、老体に鞭打って出席されたが、二次会・三次会と引っ張りだこで、各期をハシゴするほどだった。
先生のお墓のある地図を見たら交通の不便な山のなかだが、先輩たちは何人もお参りしたそうである。生徒にはそれほど人望があったのに・・・。小説では、極悪非道かのように書かれているが、旧小倉市から表彰されたし、久女も“足袋つぐやノラともならず教師妻”と作句しているが、妻である親でありながら、作句のため彼方此方と、自由奔放に出かけ、驚くことは、句友の男性を泊め、宇内は深夜に酒を買いに行ってまでもてなしたのである。明治男の心中察するに余りあり。久女の最期は哀れで薄命だったが、天才芸術家の常ではないだろうか。 謹んで 宇内・久女のご冥福を祈る。 (文中敬称略)
杉田宇内の仇名が「バネさん」であったことには、前述の久女の長女・石昌子氏も触れている。その部分を引用する。
本田
宇内先生は教育熱心だったのですね。
石
熱心でしたよ。生徒にとても絵の素質のある人がいて父もすすめたのでしょう。芸大へいって在学中に帝展に通り、卒業してフランスへ。ボナールに認められ弟子になったけど夭逝しました。
両親の嘆きを見て、もう口がくさっても生徒に、画家になれとはすすめないと。
本田
まじめな、生徒思いの先生だったのですね。
石
その父が、生徒からバネというニックネームをつけられました。本人は何とも思わないようだったけど、私は嫌でした。
本田
昔の中学の先生には、みんなついていましたよ。親愛をこめてでもあったのでしょうが。
石
私がお使いにいったとき生徒等にかこまれ、バネ、バネとからかわれて帰ったことがある。まあ、どこにでもいる悪ガキだけど、そんな事もあって母が野蛮さにいや気がさして…。
本田
まじめすぎる家庭の悲劇なんかな(笑)。では、家の中の空気は…。
石
おもたかったですね(笑)。
このことからも、ブログ『生前告別式』の杉田宇内に関する記述には信頼がおける。同じブログから記事をもう1件、こちらにはリンクのみ張っておく。
ようやく清張短編全集第3巻に話を戻す。「菊枕」に続いては*1、考古学者・森本六爾(1903-1936)をモデルとした「断碑」、同じく考古学者・直良信夫(1902-1985)をモデルにした「石の骨」が収録されている。光文社文庫版第3巻の巻末に「私と清張」を書いた作家・恩田陸に言わせれば、
「菊枕」「断碑」「石の骨」は、息苦しいまでに同じ話である。恵まれない出自の者が、自分の才能を恃みにのし上がろうとするが、学歴や家柄、組織の壁に阻まれて挫折したり不遇の生涯を送る、という話だ。
清張がおのれの生い立ちを重ね、恐ろしいまでに感情移入していることがひしひしと伝わってくるし、これを三本並べるところに強い思い入れを感じ、正直いって「ここまで並べるかあ」と聊(いささ)か引いてしまった。(光文社文庫版341頁)
とのことだ。私は「引いてしまう」ところまでは行かなかったが、「同じ話を三本並べた」という指摘には同意する。ちなみに3作の中で一番良いのは、3人のモデルの中でもっとも無名の森本六爾をモデルとした「断碑」だと思う。直良信夫は、日本にも旧石器時代はあったことが後に他の学者によって証明されたけれども、彼が発見した「明石原人」はホモ・サピエンスであったとされている。現在では「原人」ではないとする考えから、かつての「明石原人」との呼称は廃され、「明石人」と呼ばれているらしい。ここでは、清張作品に絡めて森本六爾と直良信夫について取り上げたブログ記事にリンクを張っておく。
enokidoblog.net
なお、史実で直良信夫の「明石原人」発見の手柄を横取りしようとしたとされている長谷部言人(はせべ・ことんど、1882-1969)の名前は、今年に入ってから読んだ下記のちくま新書で知ったばかりだった。
また、話が前後するが、杉田久女の師匠として名前を挙げた高浜虚子が1927年に別府温泉を訪れた時の紀行文も今年に入ってから読んだばかりだった。
清張短編全集に戻って、第3巻の6番目に置かれたのは、半自伝的作品の「父系の指」だった。この小説は、清張自身によると、
「父系の指」は、これまでの作品の中で自伝的なものの、もっとも濃い小説である。私は自分のことをナマには語りたくなかった。いわゆる私小説というものには私は不適当であり、また小説は自分のことをナマのかたちで出すべきではないという考えを持っていた。この小説でも半分くらいは事実だが、半分は虚構になっている。(光文社文庫版327頁)
とのことだ。
この小説で興味深いのはやはり主人公の生い立ちであって、清張が小倉出身とはされるものの広島県生まれであることは知っていた。小説には父の名はもちろん出てこないが峯太郎といい、今の鳥取県日南町矢戸の生まれだった。
www.yamaimo.net
しかし、峯太郎は矢戸の豪農の家に生まれながら里子に出されて窮乏生活を送り、実弟とは同じ兄弟とは思えない境遇の人生を送った。このあたりは清張の自伝『半生の記』に詳しいらしいが、新潮文庫から出ているこの本は区の図書館には置かれていないので未読だ。
興味深かったのは、小説に出てくる主人公の父が若い頃米相場で大儲けし、一時はずいぶん羽振りが良かったもののその後没落したことだ。このことから、清張の『告訴せず』に出てくる、岡山県選出衆院議員の政治資金を持ち逃げした主人公が小豆市場で一時大儲けしながら最後にお決まりの破局を迎える話を思い出した。あれは清張の父親がモデルだったんだなと思い当たった。
また、成長した主人公が矢戸を訪ねた時、広島県北部の備後落合駅で出雲の人と思われる夫婦の「東北弁のような訛」を聞くくだりを読んで、『砂の器』を思い出さない清張作品の読者はいないだろう。『砂の器』の犯人・和賀英良(わがえいりょう)の父の造形にも清張の父親の像が投影されていたことになる。とすると、和賀英良は清張自身に相当することになる。和賀英良は自分の過去を隠そうとする成り上がり者だ。
ちなみに私は、兵庫県在住の子ども時代に、小学校の担任だった女性教師その他に身近な島根県出身者がいたので、出雲の言葉が東北弁のズーズー弁と共通していることは知っていた。だから『砂の器』を読みながら、犯人は東北出身ではなく山陰出身の可能性もあるなと思いながら、登場人物の出身地に注意しながら読んでいた。和賀英良は大阪にいたことがあると書かれていたので、大阪なら山陰から出て行く人は多いし怪しいなとマークしていたのだった。だが、和賀が山陰出身であることが明かされたのは小説が犯人を明かす直前だったので、断定はできなかったのだった。なお、和賀英良の読みにはわざわざ「わがえいりょう」というルビが振ってあるのだが、ルビがなければ普通の人は「わがひでよし」と読むだろう。「わがひでよし」つまり「我が秀吉」。つまり和賀英良が作者・松本清張が造形した「成り上がり者」であることを作者自身が暗示し、それに読者が気づくかどうか読者を試しているのではないかと、これは初めて『砂の器』を読んだ時に思っていたことなのだが、その確信をますます強めた。この『砂の器』は、超音波を使った殺人のトリックが推理小説としてはルール違反に近い、いってみれば一種の欠陥作品だと私は考えているのだが、そうは言いながらこの作品の訴求力が清張作品の中でも際立って強いとも思う。こう考えると、犯人父子に焦点を当てた物語に作り変えた映画版の野村芳太郎監督は、みごとに清張の隠れた意図を読み取ったとしかいいようがない。実は私はこの映画を見たことがないのだが、一度は見なければいけないなと思った。
小説「父系の指」に話を戻すと、前記恩田陸は「私と清張」で下記のようにこの作品を高く評価している。
この三本(「菊枕」「断碑」「石の骨」=引用者註)の次に、自伝的小説「父系の指」が並ぶのであるが、本来ここに最もルサンチマン的情念が込められるべきであるのに、ここで彼の恨みが、実に完成度の高いエンターテインメントに転化されるのである。前の三編とはほぼ同じ時期に書かれているのだが、自分のことだから客観的になれたのかもしれない。(光文社文庫版341-342頁)
なるほどと思った。確かに「父系の指」は「菊枕」から始まる三部作よりも面白かった。やや長すぎるなと思わなくもなかったが。
さて、光文社文庫版短編全集第3巻で一番面白いと思ったのは、掉尾を飾る時代小説「佐渡流人行」だった。第3巻収録作の中で一番最後に書かれ、『オール讀物』の1957年1月号に掲載された。ということは書かれたのは1956年の秋だろう。清張の人気がブレイクしたきっかけとなった『点と線』は『旅』の1957年2月号から翌年1月号にかけて連載されたから、「佐渡流人行」はブレイク前夜に当たる頃の作品だ。これは時代小説ではあるが、主役が刑事というだけで特に意外な展開にもならない「張込み」よりずっと推理小説的な味わいも強いし(私は伏線には気づいていたもののあれほどのどんでん返しは予想できなかった)、また現代の企業小説にも使えそうな人間心理の描写もみごとだ。この作品についても、前記恩田陸による「私と清張」に書かれた寸評から引用する。
更に、恵まれた者への嫉妬や僻み、上昇志向といったすっかりお馴染みとなったネタを使いながら、この短篇集の中でもっともあとに書かれた「佐渡流人行」は、いよいよエンターテインメントとして洗練され、切れ味の鋭い皮肉な幕切れまで、小説としての完成度を高めているのである。
ここで、ようやく彼はおのれの負の感情を、商品としての小説に活かす術を身につけたように思える。そういう意味で、確かにこの集に作者が愛着を持つのもわかるような気がする。(光文社文庫版342頁)
ショッキングな「菊枕」もブログ記事を書く動機になったが、最後に「佐渡流人行」を読んだから、これは久々にブログにエントリを上げなければいけないなと思った次第だ。
多くの作品が資産家に私蔵され、学術的な研究が進まない日本画の世界で、真贋を良心的に鑑定する学者を師と仰いだ主人公は、所蔵家にとりいって権勢を伸ばした斯界のボスから睨まれ、陽の当たるポストから排除され続ける。彼が、才能を見込んだ田舎の美術教師を浦上玉堂の贋作者に育て上げるという計画に取りかかった時、なじみの古美術商がそれに協力するのはもちろん金目当てだ。